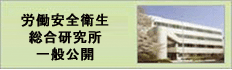夏の感電危険性について
1月に入り、本格的な冬のシーズンの到来といったところで夏の感電危険性の話題を提供することになりますが、その理由は最後まで読んでいただければ分かっていただけると思います。
感電災害が夏に多いことは既に知られているところですが、以前刊行されていた安全衛生年鑑(中央労働災害防止協会編)の統計に基づいて作成した四半期ごとの電圧別感電災害死亡者数を図1に示します。低圧電気とは、電圧が交流の場合は600ボルト以下(直流の場合は750ボルト以下)の電気のことで、家庭などのコンセントのように広く一般に使われている電気も含まれます。高圧以上とは、低圧電気を超える電圧の電気を指し、送電線や電車の架線などで使われています。図中の数字は平成8年から17年までの災害件数の合計です。高圧以上の電気では年間を通じてほとんど一定数なのに対し、低圧電気では7月から9月の四半期での発生が極端に多くなっています。年間で発生した低圧感電死亡災害の77%が夏季に集中していることになります。比率でいえば、夏季の低圧感電死亡災害は冬季の実に19倍にも達しています。低圧電気は交流600ボルト以下であまり身近ではない電圧も含まれますが、感電災害の約半分は100または200ボルトの電気で発生していることが分かっています[1]。つまり、低圧電気は年中使用されているにもかかわらず夏季に感電死亡災害が多いということは、夏季における低圧電気での死亡危険性は本質的に高いと考えられます。
![図1 四半期ごとの感電災害死亡者数(電圧別)文献[2]より引用.](192-column-2-1.png)
図1 四半期ごとの感電災害死亡者数(電圧別)文献[2]より引用
低圧電気の感電では心室細動(心臓がけいれんを起こしたような微細な動きとなること。血液循環機能が失われ、数分継続すると死に至る。)が大きな死亡原因となります。感電して心室細動が発生するかどうか、その確率は人体のどの部分に電気が流れたかにもよりますが、主には人体に流れた電流量(アンペア)と通電した時間(秒)が大きく関わることが知られています。電流量を決める要因の一つに皮膚の電気抵抗があります。電気抵抗が大きいほど電流量は小さくなるため感電危険性は下がりますが、汗や水などで皮膚が濡れていると、乾燥しているときと比べて1桁以上も電気抵抗が低くなることが分かっています。電気抵抗が低いときに感電すると、人体に流れる電流量が大きくなって心室細動の発生確率は高まります。つまり、冬季と夏季では、低圧電気で感電したときの死亡危険性が異なる可能性があります。
ここで近年の月別の感電災害についてみていきます。月別の感電死亡者数は厚生労働省が公表する「死亡災害データベース」[3]から得られます。一方で月別の感電死傷者数(感電が原因となった死亡または休業4日以上の労働災害)は、同じく厚生労働省が公表する「死傷災害(死亡・休業4日以上)データベース」[4]から集計しましたが、全件データではないため、全体の抽出率から年間発生件数(母数)を推計しました。結果を図2に示します。月別死亡者数をみると、やはり夏季(7~9月)での発生が多く、年間の60%を占めています。同じく感電死傷災害も夏季に件数が多く、年間の45%を占めていますが、死亡災害ほど冬季と夏季との差は大きくありません。この統計では低圧と高圧以上の電圧の分類ができていませんが、近年の感電死亡災害の半数以上は低圧電気の感電であることが分かっています[5]。
![図2 月別の感電災害発生件数(死亡者数は確定値,死傷者数は推定値)文献[2]より引用](192-column-2-2.png)
図2 月別の感電災害発生件数(死亡者数は確定値,死傷者数は推定値)文献[2]より引用
次に、感電危険性の大きさについて、感電災害における死亡災害の占める割合(感電死亡災害割合)を使って考察してみます。平成18年から令和3年までの月別の感電死亡災害割合を計算した結果を図3に示します。これをみると、7月では20%、8月では17%と他の月よりも高くなっています。つまり、夏季では感電死亡災害に至る危険性が高いと考えられます。先に述べたように、低圧の感電死亡災害は高圧以上の災害を上回る傾向が見られているため、感電死亡災害を減少させるためには、低圧電気の感電災害を一層減少させることが課題となってきています。これには、夏季における低圧電気の感電災害を減らすことが大きなポイントであるといえます。
![図3 感電死傷災害のうち死亡災害が占める割合(月別)文献[2]より引用.](192-column-2-3.png)
図3 感電死傷災害のうち死亡災害が占める割合(月別)文献[2]より引用
夏季に感電災害が多い理由として、電気関係の労働者が絶縁用保護具等の使用を怠りがちになること、軽装により直接皮膚を多く露出すること、注意力が低下しがちであることなどが考えられており、平成13年には、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長より「夏季における感電災害の防止について」の通達[6]も出ているので再確認していただきたいと思います。
加えて、夏は汗をかくなどによって皮膚の電気抵抗も下がる傾向があるため、低圧電気と接触したときに心室細動を引き起こしやすくなるという考察から、冬には命に別条のなかった感電のヒヤリ・ハットでも、同じことが夏に起これば死亡するといったことも考えられます。このようなことから、夏の感電災害を減らすには、夏だけ感電に気を付ければよいということではなく、常日頃から感電のヒヤリ・ハットを見過ごさないことが大切です。漏電、プラグ等の破損、絶縁被覆の劣化などを発見したら、必ず直ちに対処しなければならなりません。また、点検によって不具合箇所を見つけ出し、早急に対処することが、夏の感電死亡災害を防ぐことにもつながります。電源コードの差し込み(コンセント・プラグ)の絶縁物(プラスチック)が欠けたまま使用し続けて感電死亡災害に至った事例や、定期点検で漏電の不具合が発見されていながら対処していなかったために感電死亡災害に至った事例は「職場のあんぜんサイト」[7]などで確認することができます。
参考文献
- 低圧電気取扱者安全必携‐特別教育用テキスト‐,中央労働災害防止協会
- 三浦崇.統計でみる感電災害の特徴‐夏の感電危険性,北海道のでんき 第772号(2024年8月)p6.
- 厚生労働省.死亡災害データベース.職場のあんぜんサイト.https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.html(2024年12月14日)
- 厚生労働省.死傷災害(死亡・休業4日以上)データベース.職場のあんぜんサイト.https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(2024年12月14日)
- 冨田一.感電死亡災害の現状分析とリスクアセスメントの試み,労働安全衛生研究14(2021)177.(J-Stage)
- 夏季における感電災害の防止について,基安安発第23号の2 https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-42/hor1-42-38-1-0.htm(中央労働災害防止協会)
- 厚生労働省.労働災害事例.職場のあんぜんサイト.https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx(2024年12月14日)