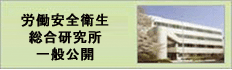| 1) | 小嶋 純(2008)溶接粉じんの個人ばく露濃度測定法の提案.労働安全衛生研究 1,265-267.
|
| 2) | 高橋正也,三浦伸彦,東郷史治,樋口重和,毛利一平(2008)ヒトの睡眠研究の進歩(時計遺伝子と疾患).細胞工学 27(5),436-441.
|
| 3) | 小嶋 純(2008)溶接作業者の粉じんばく露濃度測定.セイフティダイジェスト 54(4),7-9.
|
| 4) | 高橋正也(2008)概日リズム性睡眠障害–交替勤務型(交替勤務性障害).睡眠臨床学–睡眠障害の基礎と臨床.日本臨牀(増刊) 66,341-343.
|
| 5) | 高橋正也,三浦伸彦,東郷史治,樋口重和,毛利一平(2008)ヒトの睡眠研究の進歩.『眠り』をめぐるバイオロジー.細胞工学27,436-441.
|
| 6) | 前田節雄(2008) し・ん・ど・うの科学 4課題が残る手腕振動障害の実態. 労働の科学, vol 63, pp 228-230. |
| 7) | 岩崎健二(2008)長時間労働と健康問題–研究の到達点と今後の課題.日本労働研究雑誌 2008年6月号, p39-48.
|
| 8) | 前田節雄 (2008) し・ん・ど・うの科学 5手腕振動の評価〈1〉計測の計画と実施. 労働の科学, vol 63, pp 296-299. |
| 9) | 柴田延幸,前田節雄(2008)新JIS T8114に基づいた軍手の振動伝達軽減性能の測定・評価.セーフティダイジェスト 54(5),9-14.
|
| 10) | 原谷隆史(2008)職場のハラスメントに関する用語と最近の動向.産業精神保健 16(2):108-114.(5月12日発行,6月号)
|
| 11) | 高橋正也(2008)職場との連携ガイドライン.特集 睡眠障害の診断・治療ガイドライン.睡眠医療 2,333-336.
|
| 12) | 前田節雄 (2008) し・ん・ど・うの科学 6手腕振動の評価〈2〉計測データの評価. 労働の科学, vol 63, pp 368-372. |
| 13) | 前田節雄(2008) し・ん・ど・うの科学 7手腕振動の評価〈3〉日振動ばく露量を用いた影響評価方法. 労働の科学, vol 63, pp 414-417. |
| 14) | 甲田茂樹(2008)今,改めて考えたい 災害防止への道–安全で健康的な職場を目指して,効果的な安全衛生活動を展開する–.地方公務員安全と健康フォーラム18(3),10-14.
|
| 15) | 倉林るみい (2008) 働く人のメンタルヘルス:日本の最近の問題点. 応用科学学会誌22,12-18.
|
| 16) | 岩切一幸(2008)介護施設における腰痛予防対策.労働安全衛生広報 40,14-21.
|
| 17) | 森永謙二,篠原也寸志(2008)労災補償と救済.臨床検査,52,1039-1044.
|
| 18) | 前田節雄(2008) し・ん・ど・うの科学 8手腕振動の評価〈4〉試験規則:宣言値の導出方法. 労働の科学, vol 63, pp 494-497. |
| 19) | 岩切一幸(2008)介護事業における腰痛の発生状況と予防対策のポイント.安全と健康 59,34-37.
|
| 20) | 前田節雄(2008) し・ん・ど・うの科学 9手腕振動ばく露軽減対策方法〈1〉–工具のラベリング–. 労働の科学, vol 63, pp 556-559. |
| 21) | 前田節雄(2008) し・ん・ど・うの科学 10手腕振動ばく露軽減対策方法〈2〉–宣言値を用いた作業管理–. 労働の科学, vol 63, pp 618-620. |
| 22) | 小嶋 純(2008)安政五年の防じんマスク.セイフティダイジェスト 54(11),8-11.
|
| 23) | 前田節雄 (2008) し・ん・ど・うの科学 11手腕振動ばく露軽減対策方法〈3〉–防振手袋–. 労働の科学, vol 63, pp 684-686. |
| 24) | 前田節雄(2008)し・ん・ど・うの科学 12手腕振動ばく露軽減対策方法〈4〉–作業管理へのアイディア–. 労働の科学, vol 63, pp 742-744. |
| 25) | 鈴木 薫,小泉信滋(2009)産業化学物質がヒト遺伝子に及ぼす影響の評価–レポーターアッセイの活用–.労働安全衛生研究 2(1),53-56.
|
| 26) | 久永直見,榊原洋子,酒井 潔,齊藤宏之(2009) 大学の研究室で生じた不快臭による吐気 –発生源追求と対策–. IRIS HEALTH(愛知教育が医学保健環境センター紀要) 7, 21-25.
|
| 27) | 荒川泰昭,小川康恭,荒記俊一(2009)微量元素の代謝と生理的機能.臨床検査 53(2), 149-153.
|
| 28) | 荒川泰昭,小川康恭,荒記俊一(2009)微量元素と免疫機能.臨床検査 53(2), 191-196.
|
| 29) | 高橋正也.睡眠と交替制勤務(2009)睡眠とその障害 A: 睡眠医学の基礎.Clinical Neuroscience 27, 152-153.
|
| 30) | 高橋正也(2009)健康増進・労働安全衛生の視点からスリープ・リテラシーを考える.綜合臨牀 58, 398-405.
|
| 31) | 甲田茂樹(2009)職場におけるナノマテリアル取扱いについて.安全衛生コンサルタント Vol.29,No.89, 24-27.
|
| 32) | 甲田茂樹(2009)ナノマテリアル取り扱いと労働衛生の課題.労働の科学 64(4), 13-15.
|
| 33) | 小嶋純(2009)小型内燃機関による一酸化炭素の防止と全体換気,労働安全衛生研究,2-1, pp. 57-61
|
| 34) | 濱島京子,梅崎重夫(2008)ITを活用した新しい安全管理手法に関する研究,労働安全衛生広報,40-938, pp. 15-23
|
| 35) | 崔光石,冨田一,中田健司,鄭載喜(2008)韓国における配電電圧の昇圧化事業,OHM,6, pp. 26-29
|
| 36) | 高木元也(2008)建設業における労働災害損失額計測手法の構築について,安全衛生コンサルタント,28-87,pp. 30-38
|
| 37) | 八島正明(2008)爆発・火災を起こさないための基礎知識(4)–爆発と火災の概要–,化学装置,50-7,pp. 90-98
|
| 38) | 伊藤和也,豊澤康男(2008)斜面崩壊による労働災害の調査分析と対策,建設の施工企画,701,pp. 77-82
|
| 39) | 高木元也(2008)中小建設業者におけるリスク適正評価のための課題と対策,建設オピニオン,15-7,pp. 28-37
|
| 40) | 永田久雄(2008)安全靴のJIS規格と耐滑性の測定法について,トライボロジスト,8, pp. 524-529
|
| 41) | 齋藤剛(2008)機械の安全設計の基本原則–ISO12100のリスク低減プロセス–,日本信頼性学会誌,30-6,pp. 546-551
|
| 42) | 市川紀充(2008)感電防止用保護具及び防御具等–2050年までに感電死亡災害ゼロを目指す!–,第1種電気工事士のための電気工事技術情報,26,pp. 18-22
|
| 43) | 高木元也(2008)中小建設業者におけるリスク適正評価に関する課題,労働安全衛生広報,40-949
|
| 44) | 山隈瑞樹(2008)静電気による爆発・火災の発生機構と対策,Safety & Tomorrow,122, pp. 2-10 |
| 45) | 高木元也(2008)中小・中堅建設業者を対象としたリスクマネジメント推進のためのアクションプログラム–労働災害の更なる防止に向けた行動指針–,建設業しんこう,33-9
|
| 46) | 濱島京子,梅崎重夫,木吉英典,中北輝雄(2008)ITを活用した安全管理手法,セイフティ・エンジニアリング,35-5, pp. 152-
|
| 47) | 中村隆宏(2009)産業安全とヒューマンファクター–クレーン操作時の注視対象を例に–,Jitsu・Ten 実務&展望,247,pp. 49-55
|
| 48) | 高木元也(2009)災害多発分野(建設,機械,化学)におけるリスクマネジメント推進に関わる産業横断的事例研究–各分野で異なる「システムの良点」 手法を他業種へ展開しRMに活かせ!–,労働安全衛生広報,41-954,pp. 32-35
|
| 49) | 齋藤剛(2009)機械のリスクアセスメントの実施手順,日本信頼性学会誌,31-1, pp.53-58
|
| 50) | 八島正明(2009)爆発・火災をおこさないための基礎知識(5)–粉体の爆発と火災(その1),化学装置,51-2, pp. 69-83
|
| 51) | 八島正明(2009)爆発・火災をおこさないための基礎知識(6)–粉体の爆発と火災(その2),化学装置, 51-3, pp. 90-97
|
| 52) | 中村隆宏(2009)安全管理とメンタルヘルス,産業精神保健,17-1, pp. 17-21
|
| 53) | 大幢勝利(2008)仮設構造物の安全–足場,型わく支保工について–,安全工学,47-3,p.126-132
|
| 54) | 中村隆宏(2009)安全教育としての危険体験の展開,安全工学,47-6, pp. 383-390
|
| 55) | 深谷潔(2009)フルハーネス型安全帯の必要性に関する研究紹介,労働安全衛生研究,2-1, pp. 49-52
|
| 56) | 梅崎重夫,清水尚憲,濱島京子(2008)機械のリスクアセスメント - 機械安全と労働安全の連携を考慮したリスクマネージメント戦略の提案 -,日本信頼性学会誌,Vol.30, No.8 pp.692-702 |