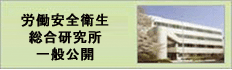任期付研究員として採用された先輩の声:清瀬地区(産業安全分野)
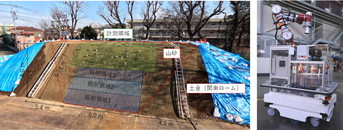
任期付研究員として採用された研究員は、審査を経てほとんどの方が任期を付さない研究員として新たに採用されています。定年まで安定して働けるようになり、以下にご紹介するように充実した研究活動を行っています。
機械システム安全研究グループ 主任研究員 緒方 公俊
令和2年に任期付研究員として採用、令和5年に任期を付さない研究員として採用
材料力学、破壊力学の専門分野を活かして、ワイヤロープの破断防止に関する研究に携わっています。クレーンやエレベータなどで使用されるワイヤロープの破断事故防止は、重篤な労働災害を防止するための重要な研究テーマの一つです。任期付研究員として赴任して間もなく、この研究プロジェクトの一因として参加させていただき、研究に励んでいます。また、当所が担う重要業務である労働災害調査にも参加することができました。自身の専門分野と経験をフル活用し、実際に発生した労働災害に対して現場調査、情報収集、検証試験を通じて発生原因を究明し、再発防止を立案する本調査は、非常にやりがいのある業務です。
当研究所には充実した実験環境や、気軽に諸先輩方に相談、議論できる職場環境が整っていると感じています。そのため特に不安を感じることなく日々研究に取り組むことができ、赴任後の3年間で多くの業績を挙げることができました。任期を付さない研究員になり、現在(執筆時)は当所の海外派遣制度を活用し、ドイツの研究機関に滞在する機会を頂きました。赴任当時から現在に至るまで恵まれた研究環境のもとで、充実した研究生活を送ることができています。
建設安全研究グループ 研究員 金 惠英
令和4年に任期付き研究員として採用、令和7年に任期を付さない研究員として採用
現在、建設現場における労働災害防止のため、2つの研究に取り組んでいます。1つ目は、強風時の足場倒壊災害に関する研究で、特に解体工事で使用される防音パネルの影響を風洞実験により検証しています。2つ目は、低所からの墜落・転落による頭部外傷リスクに関する研究で、人体モデルやダミーを用いた衝突解析・実験を行っています。これまで構造物の地震・風によるリスク評価を行ってきましたが、研究所入所後は、より実践的に労働者や利用者の安全に直結する研究へと視野を広げています。研究所には風洞・構造・墜落実験棟など、建設安全に関する研究に必要な設備が整っており、優れた研究環境が整備されています。
化学安全研究グループ 主任研究員 西脇 洋佑
令和2年に任期付研究員として採用、令和5年に任期を付さない研究員として採用
労働者が関わる爆発・火災災害は、危険な化学物質を製造するような化学設備を有する工場だけでなく様々な業種でも発生し続けており、その物質の種類や形態も様々となっています。爆発・火災災害を防ぐためには化学物質の危険性を把握し、適切な対策を講じる必要があり、それら危険性の調査・評価手法や実際に爆発・火災を起こした物質での災害発生までの現象、災害防止対策について研究を行っています。
また、実際の労働災害現場へ赴いての原因調査や国際的な化学物質管理基準策定への行政的な立場からの参加など、自身の研究を社会に直接反映することができると共に、通常では触れられない情報や研究ニーズも把握できるような貴重な経験を積むことができています。
入所時は労働災害に関する法令の知識が乏しかったこともあり、仕事に不安はありましたが、先輩方の手助けを頂くことができ、研究やその他の業務を進めることができています。特に任期付研究員へのサポートは所属グループを跨いで手厚く、その文化は継承していければと考えています。日本の労働安全衛生のためにも、当所への入所者をお待ちしております。
電気安全研究グループ 研究員 庄山 瑞季
令和4年に任期付研究員として採用、令和7年に任期を付さない研究員として採用
労働現場において粉じん火災・爆発の要因となり得る静電気放電の抑制に関する研究を行っています。入所前は、大学で粉体の帯電現象や静電気力を利用した粉体操作についての研究に従事しており、研究テーマが社会の需要とマッチしているか疑問に思うことがありましたが、入所後、企業からの相談や災害調査を経験することで、社会における自分の研究の重要性や役割が明確になりました。
当研究所は、実験設備や研究スペース、技術的サポートなどの研究環境が整っており、各分野における優秀な研究者も多数在籍しているので、充実した研究活動を行うことができます。さらに、得られた研究成果を学会発表や論文で公表するだけでなく、法令や基準、技術指針などに反映させ、産業現場で働く人たちの安全に貢献することができます。興味がある方は、是非一度見学に来てください。
リスク管理研究グループ 主任研究員 柴田 圭
令和3年に任期付研究員として採用、令和6年に任期を付さない研究員として採用
労働災害として近年多く発生している転倒災害に関する研究を行っています。現在は、床面と靴底の間のすべりを簡易的に評価できる手法の開発に携わっており、例えば、人の感覚によりすべりを評価することはできないか、または、靴底や床面の写真を撮るだけですべりを予測できないか、といったことを考えています。このような簡便なすべりの評価ができれば、労働災害はもちろん、日常生活にも応用できると期待しています。
研究所に入所する前には、大学にて樹脂や金属材料の摩耗を減らす材料開発に関する研究を行っていました。これはトライボロジー(摩擦学)という分野になります。入所前には労働災害に関する研究に関わったことがなく、かなり不安を感じていました。入所後も労働災害という巨人に対してどう対応したらいいのか考えあぐねることもありましたが、徐々に、これまでに得た研究知識や経験をツールとして労働災害の分野に活かすという考え方にシフトしていくことにより、道が拓けたと思っています。現在では、人命を守るという社会に必要不可欠な分野でやりがいのある研究や調査を行っていると実感しています。日々,頼もしい研究所の専門家達に刺激を受けながら、協力して労働災害防止に向けて研究や調査を進めています。
新技術安全研究グループ 研究員 平内 和樹
令和3年に任期付研究員として採用、令和6年に任期を付さない研究員として採用
腰痛や転倒等の労働者の作業行動に起因する労働災害防止のための研究をしております。私の専門は、職場の人間工学、特に作業姿勢や動作の変化によって生じる身体負担や作業性の評価に関する研究を行っていました。当研究所に採用されて以降も、その専門知識を活かした研究を行うことができています。
労働者の作業行動に起因する労働災害の防止では、対策のノウハウがまだ十分ではなく、対策に寄与する知見を得て提供していくことから求められており、そのニーズに応えていくことに非常にやりがいを感じています。当研究所は社会的なニーズの高い研究を行う機関であり、成果の積極的なアウトプットが求められます。このため、実際に現場で働く方々や行政等との連携を図りながら、今後は、研究成果の普及実装のための技術開発等にも取り組んでいきたいと考えています。